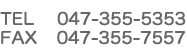がんよろず相談外来 担当:竜 崇正(前千葉県がんセンター長、千葉県がん対策審議会副委員長)
「がん」になってどう向き合ったらいいのか、今受けている治療がこれでいいのだろうか?再発したらしいけどどうしたらいいかしら、家で過ごしたいけれど、など「がん」になったとたんに、人生の最大の難問が降りかかってくると思います。私のがん外科医としての経験と知識、そして幅広い人脈であなたの悩みの相談に乗ります。
治療法を相談するために詳しい検査を急いでしたい方は、毎週木曜日に私が千葉県がんセンターで行っている「がんよろず外来」で検査をしますので、受診当日にはかなりの結論が出せると思います。
1) 相談と適切な治療のアドバイス。
2) がんの診断と広がり診断
3) 心と体の苦痛に対する治療とカウンセリング
4) 適切な治療施設の紹介
5) 在宅ケア―の提供やコンサルティング

人はなぜ「がん」になるのか
1)「がん」は遺伝子に傷がついておこる病気
ヒトの細胞の核にあるDNAに組み込まれた遺伝子情報がゲノムです。ゲノムは、アデニン(A)、グアニン(G),シトシン(C)、チミン(T)の4種類の塩基が結合する30億の塩基対からなる生命の設計図です。この遺伝子に傷がついて、がん遺伝子が活性化したり、がん抑制遺伝子が不活性化して、1個の細胞から無限に増え死なない「がん細胞」ができ、その発生母体である人の命を奪うのです。
「がん遺伝子」が増えると、いわばアクセルが踏まれっぱなしの状態となり、「がん抑制遺伝子」が減ると、いわばブレーキが利かない状態になって、がん細胞が無限に増殖するのです。
2)生命の維持に必要な遺伝子の突然変異で「がん遺伝子」が発現
1982年にがん遺伝子RASが発見されました。このRASの発見で「がん」の治療は大きく進歩するものと期待されました。しかしRASは全ての生物の正常細胞の中にもあったのです。正常細胞のRASとがん細胞のRASを比較する研究で6500の塩基の中のたった一つの塩基がGGCからGTCに変化していただけなのです。生命維持に必要な遺伝子のわずかの変化が、「がん」を引き起こすのです。ここに「がん治療」の非常に困難な壁があるのです。
「がん」の遺伝子異常は1つだけではありません。無限に増え続ける「がん細胞」の特徴を維持する仕組みは複雑で、数100の遺伝子異常が連鎖的に起こっているのです。
3)がんの遺伝子治療への期待
したがって、遺伝子治療は簡単ではありません。各「がん」に特徴的な遺伝子異常を探し、それに対抗する新薬の開発に、世界中がしのぎを削っています。しかし、強い遺伝子異常が原因の場合、その治療薬(分子標的治療薬)により、がんの進行や転移を抑える治療薬も実際に使われています。EGFが多く発現している非小細胞肺がんには、イレッサが極めて有効で、多発脳転移や肺転移が消失する方も少なくありません。
4)がん予防のためには
遺伝子を傷つける要因は、放射能、タバコやアスベストなどの化学物質、ウイルスや細菌感染、加齢などです。因果関係が明らかな胃がん予防のためのピロリ菌除菌や、肝炎ウイルス治療による肝細胞がん予防、抗パピローマウイルスワクチンによる子宮頸がん、など遺伝子に傷つける要因を取り除くことで、がん予防は可能です。前項で述べた「禁煙」はすぐできるがん予防対策です。
胃がん予防とピロリ菌除菌
胃がんの死亡率は2011年で第2位、第1位は肺がんです。しかし胃がんの罹患率は依然として第1位であり、生涯に胃がんで死亡するリスクは男性で25人に1人、女性で55人に1人と、恐ろしいがんであることに変わりはありません。胃がんで命を落とさないような対策が必要です。
日本では早くからがん検診が積極的に行われており、集団検診ではバリウムによる胃2重造影X線検査が行われています。しかしがん検診受診率は30%と低く、毎年同じ人が受けているため発見率は低く、効果的に早期がんを診断するには限界があります。
近年、胃がんとピロリ菌の関係が明らかになってきました。ピロリ菌は衛生状態の悪い環境で感染するもので、戦争後の時代を過ごした年齢層ほど感染率が高く、若年者では著しく低い感染率となっています。感染すると、胃粘膜の広範な炎症が起こり、ひどい萎縮性胃炎となり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、MALTリンパ腫、過形成ポリープ、胃がんなどの原因となります。特に強い胃炎が胃全体に広がっている場合は、未分化癌が発生しやすくなります。
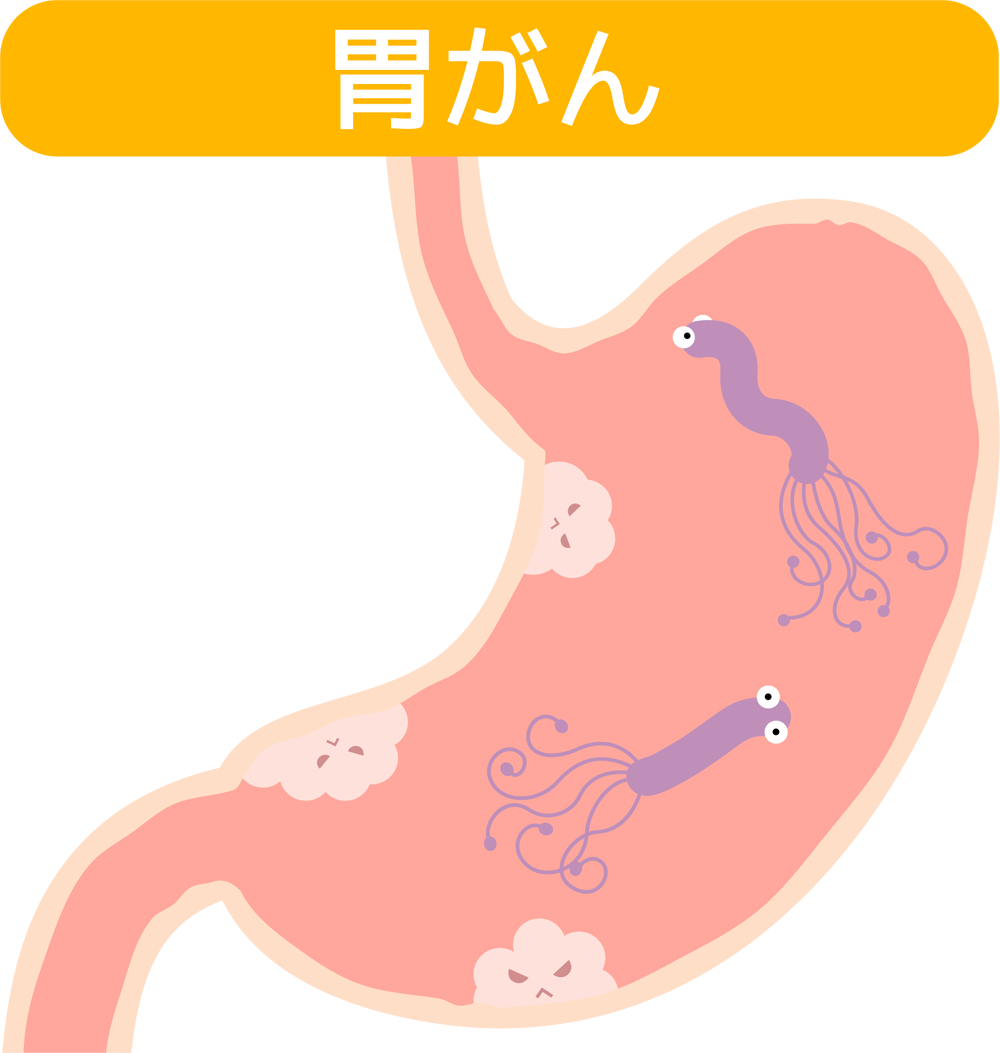
胃がん予防のためのピロリ菌除菌は、健康保険で認められていませんが、早期がんの内視鏡的治療後や胃切除後、にピロリ除菌した方の胃がん再発率が1/3と圧倒的に少なかったことから、保険適応にしようという動きも広がっています。内視鏡や胃バリウム検査で慢性萎縮性胃炎と診断されれば、健康保険でピロリ菌を除菌できます。ピロリ菌に関係しない胃がんの発生は極めてまれですので、胃がん予防のためには積極的に除菌をすることが大切です。
ピロリ菌の感染の診断は、内視鏡での標本から、ウレアーゼ呼気テスト、血液検査、便の検査などから行うことができます。除菌にはアモキシシリンとクラリスロマイシンの2種類の抗生物質をプロトンポンプ阻害薬という胃薬と共に1週間服用します。2007年での除菌成功率は85%でした。
除菌効果判定は、治療終了後2か月程度で、便の検査で行います。最近は風邪などでの乱用によりクラリスロマイシンの耐性菌が増加しており、除菌成功率は75%前後に低下しています。不成功の場合はメトロニダゾールを用いての2除菌を行い、こちらは耐性菌が2%前後と少なく90%以上の除菌成功率となります。
除菌に伴う副作用は、2倍量の抗生剤服用による下痢や吐き気などが15%の方にみられますが,軽度な服薬をあきらめるほどの副作用は極めて少ないと思います。
胃がんから命を守るために、胃内視鏡検査を積極的に受け、ピロリ菌に感染している方は除菌をしましょう。
喫煙と肺がん
肺がんの最大の原因は喫煙である。喫煙を開始する年齢が低ければ罹患する可能性が増し、また自分が喫煙しなくとも周りの人が喫煙すれば肺がんになる可能性が20-30%高くなると言われる。
1日あたりの喫煙するタバコの本数と喫煙している年数をかけ合せた数字(喫煙指数)が600以上の人は肺がんの高危険群である。概して喫煙者の肺がん死亡リスクは非喫煙者の4倍から5倍、それも喫煙量が1日あたり20本以上なら10倍以上であり、喫煙開始年齢が低いとさらに増加することは前述の通りである。
小細胞肺癌
小細胞肺癌は肺癌の20%程度を占める。喫煙との関連性が大きいとされ、中枢側の気管支から生ずることが多い。悪性度が高く、急速に増大・進展し、またリンパ行性にも血行性にも早いうちから脳などの他臓器に転移しやすいため、発見時すでに進行がんである事が多い。がん遺伝子としては L-myc が関わっている。
免疫染色によるマーカーの同定や電子顕微鏡撮影により、カルチノイドなどと同じく神経内分泌上皮由来であることがつきとめられている。診断時に既に転移が見られることが多いため、化学療法、放射線療法が行われることが多い。放射線療法、化学療法に対して比較的感受性があるものの、多くは再発するため予後はあまり良くない。
しばしばランバート・イートン症候群(Lambert-Eaton syndrome; LEMS)などの傍腫瘍症候群を合併する。血液検査では、ProGRPや神経特異的エノラーゼ (NSE) が腫瘍マーカーとなる。時に副腎皮質刺激ホルモンや抗利尿ホルモンなどのホルモンを分泌することがあり、クッシング症候群や抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) の原因となる。
非小細胞肺癌
以下の3組織亜型があり、治療上の観点から一括して総称される。
肺扁平上皮癌
肺扁平上皮癌(はいへんぺいじょうひがん、Squamous cell carcinoma)は、気管支の扁平上皮(英語版)(厳密には扁平上皮化生した細胞。生理的には、扁平上皮は気道においては口腔や声帯など上気道の一部の細胞であり、正常な下気道のどこにも扁平上皮は存在しない)から発生する癌。
喫煙との関係が大きく、中枢側の気管支から生ずることが多い。喀痰細胞診では、パパニコロウ染色にて扁平上皮細胞から分泌されたケラチンがオレンジに染まることが特徴的である。病理組織学的検査では、扁平上皮細胞の球から内側に分泌されたケラチンが纏まり真珠のように見られることがあり、癌真珠とよばれる。血液検査ではSCC、CYFRA(シフラ)が腫瘍マーカーとなる。
肺腺癌
肺腺癌(はいせんがん、Adenocarcinoma)は、肺の腺細胞(気管支の線毛円柱上皮、肺胞上皮、気管支の外分泌腺など)から発生する癌。発生部位は肺末梢側に多い。喫煙とも関連するが、非喫煙者の女性に発生する肺癌は主にこの型である。病理組織学的には、がん細胞は腺腔、乳頭状、微小乳頭状、充実性構造を作る。血液検査ではCEA(癌胎児性抗原)、SLX(シアリルルイスX抗原)などが腫瘍マーカーとなる。
肺大細胞癌
肺大細胞癌(はいだいさいぼうがん、Large cell carcinoma)は、扁平上皮癌にも腺癌にも分化が証明されない、未分化な非小細胞肺癌のことである。発育が早く、多くは末梢気道から発生する。
肺内の気道粘膜の上皮は、たばこの成分などの、発癌性物質に曝露されると速やかに、小さいながらも変異を生じる。このような曝露が長期間繰り返し起こると、小さな変異が積み重なって大きな傷害となり、遂には組織ががん化するに至る。腫瘍が気管支腔内へ向かって成長すれば気道は閉塞・狭窄(きょうさく)し、場所と程度によってはそれだけで呼吸困難を起こす。
気道が完全に閉塞すれば、そこより末梢が無気肺となり、細菌の排出が阻害されることにより肺炎を生じやすくなる(閉塞性肺炎)。また、腫瘍の血管はもろく出血しやすいため、血痰を喀出するようになる。一方、気管支の外側への腫瘍の成長は、他の臓器に転移するまでは、それ自体による身体的症状を起こしにくい。
一般的な症状は、血痰、慢性的な激しい咳、喘鳴(ぜんめい)、胸痛、体重減少、食欲不振、息切れなどであるが、進行するまでは無症状であることが多い。